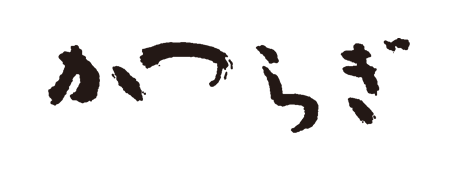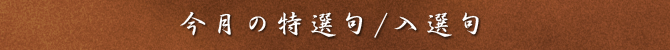
2025年12月16日~2026年1月15日締切分
森田 純一郎選(新ウェブ句会より)
特選 三句
-
43
巫女溜りへと運ばるるどんど餅
木村由希子
-
82
ふつと天仰ぎてよりの射初めかな
村手圭子
-
41
熱々の焼芋包む新聞紙
井野裕美
秀逸 五句
-
88
香水の小瓶に納め針入るる
(・・・・・入れて納め針)前田野生子
-
90
一段目地にすれすれや楮干す
古谷多賀子
-
72
初鏡素直に老いを受け入れぬ
平田冬か
-
6
どんどの香させて塾の子入りくる
(塾の子の入りくるなりどんどの香)安田純子
-
38
大空にパッと大の字梯子乗
山崎圭子
特選 三句
-
特選1
巫女溜りへと運ばるるどんど餅
木村由希子
神社でどんど焼をする時に、どんどの火でお餅を焼いて来ている人に振舞うのでしょう。そのお裾分けを巫女溜りの巫女さん達にも運んだいたのでしょう。目の付け所の良い新鮮などんどの句です
-
特選2
ふつと天仰ぎてよりの射初めかな
村手圭子
新年の弓道場での弓始の行事の時には射手も普段とは違う緊張感があるのだと思います。まずは天を仰いで、ふっと息を吐いてから矢に弓をつかえるのでしょう。何となく女性の射手を思います
-
特選3
熱々の焼芋包む新聞紙
井野裕美
珍しい焼芋の句です。最近はあまり見掛けませんが、小学生の頃、焼芋屋さんの屋台が来るとワクワクして買いに行ったものです。いつも古新聞にくるんで渡してくれました。思い出に共感します
秀逸 五句
-
秀逸1
【88】
香水の小瓶に納め針入るる
(・・・・・入れて納め針)前田野生子
針供養で納める針を香水の小瓶に入れているという女性らしい句です。季語はもちろん納め針です
-
秀逸2
【90】
一段目地にすれすれや楮干す
古谷多賀子
紙漉用の楮は段々に組んだ木に掛けて干すのですが、一段目は地面すれすれです。よく見て写生しています
-
秀逸3
【72】
初鏡素直に老いを受け入れぬ
平田冬か
新年になって鏡に向かった時に自分の顔を見て老いを感じたのでしょう。素直に受け入れることが素晴らしいです
-
秀逸4
【6】
どんどの香させて塾の子入りくる
(塾の子の入りくるなりどんどの香)安田純子
どんど焼をしたのか見ていた子供たちが塾にやって来たのでしょう。技巧を凝らさず平明に詠めばいいです
-
秀逸5
【38】
大空にパッと大の字梯子乗
山崎圭子
出初式での光景でしょう。中七の「パッと大の字」が印象明瞭にその様子を伝えています
入選
入 選 句
-
【19】
我が町に教会二つクリスマス
木村由希子
-
【20】
小説に泣かされてゐる炬燵かな
糸賀千代
-
【24】
空透けてくれば漬け頃大根ハザ
平田冬か
-
【27】
宮内庁納入の紙厚く漉く
古谷彰宏
-
【31】
床払ひ玉の緒深く初湯殿
(・・・・・・・初湯かな)吉浦 増
-
【37】
指揮棒の止まる瞬間年明くる
吉川やよい
-
【39】
罅割れの餅もて鏡開きせり
角山隆英
-
【44】
七彩の溢るる菓子や女正月
村手圭子
-
【55】
和紙の里底に沈めて山眠る
古谷彰宏
-
【56】
湯呑には茶柱すくと節料理
黒岩恵津子
-
【67】
特大の戎笹乗る島渡船
武田順子
-
【68】
スピーチの長く寄鍋湯気上げる
広田祝世
-
【69】
料亭の赤い番傘雪しぐれ
西岡たか代
-
【74】
屠蘇の底三つ杉確と浮かべけり
角山隆英
-
【79】
七草の粥に野の色息吹きをり
大久保佐貴玖
-
【80】
向き合ひて御慶申して六十年
中内ひろこ
-
【86】
あかつきの雲の高さを初鴉
大久保佐貴玖
-
【102】
ひとたびは掌にのせ雛飾る
前田野生子
入選
佳 作 句
-
【11】
これでもかと釜に詰め込み楮束
古谷多賀子
-
【12】
鐘一打一打に夜の凍てにけり
(・凍る・・・・更けり)大久保佐貴玖
-
【14】
初日燦十九階のリビングに
たなかしらほ
-
【21】
初日影一木一草一石に
平田冬か
-
【36】
どんど火に真向き背きに吾が髪膚
山崎圭子
-
【53】
ババ抜きのババまた掴む炬燵かな
たなかしらほ
-
【75】
みはるかす棚田に一人農初め
宮原昭子
-
【92】
初稽古アン・ドゥ・トロワと始まりぬ
(・・・・・・・・トワロ・・・・)峰村ひさ子
-
【93】
聞かなくてよい事もあり日向ぼこ
近藤八重子
-
【97】
甲山見下す池に鴨遊ぶ
森田教子
-
【101】
春灯す俳諧指針を示す書に
武田順子
-
【107】
吉兆の鈴の音響くバス車内
黒岩恵津子
純一郎吟
-
【23】
アーケードB G Mはお正月
-
【57】
煤逃に巡る浪速の資料館
-
【89】
数へ日の天牛書店閉ざしけり